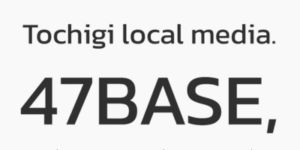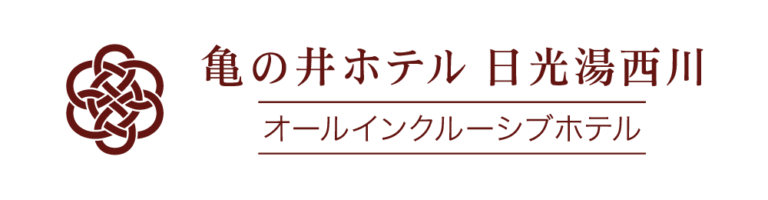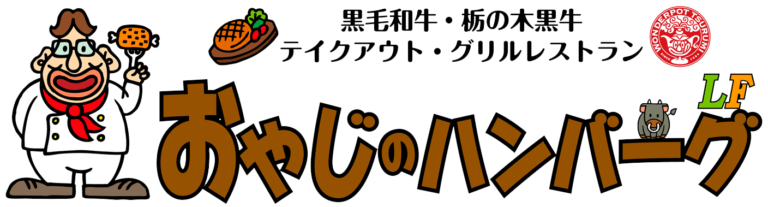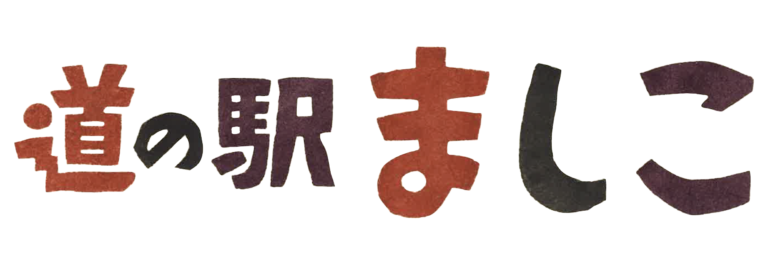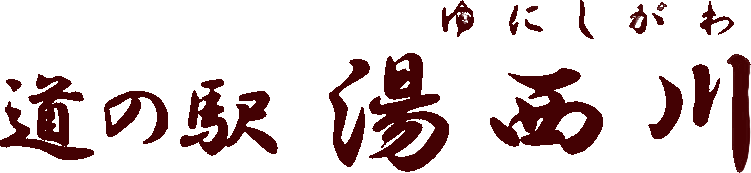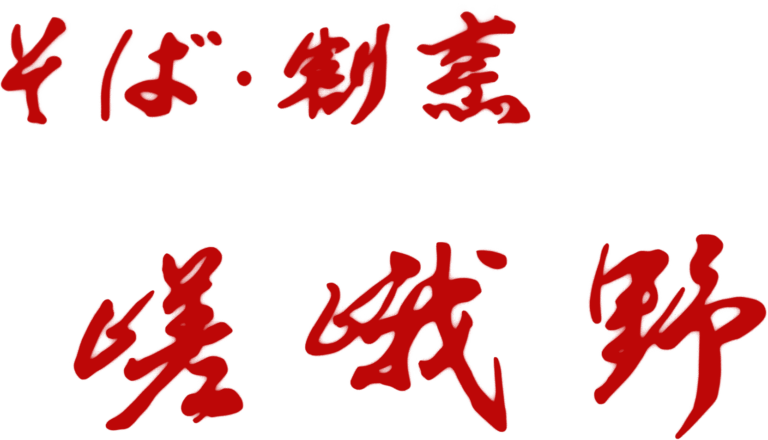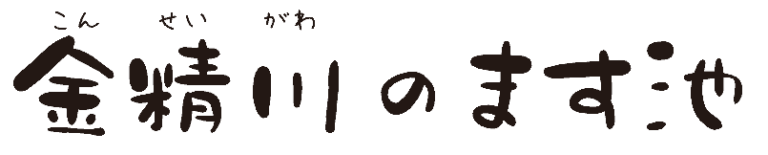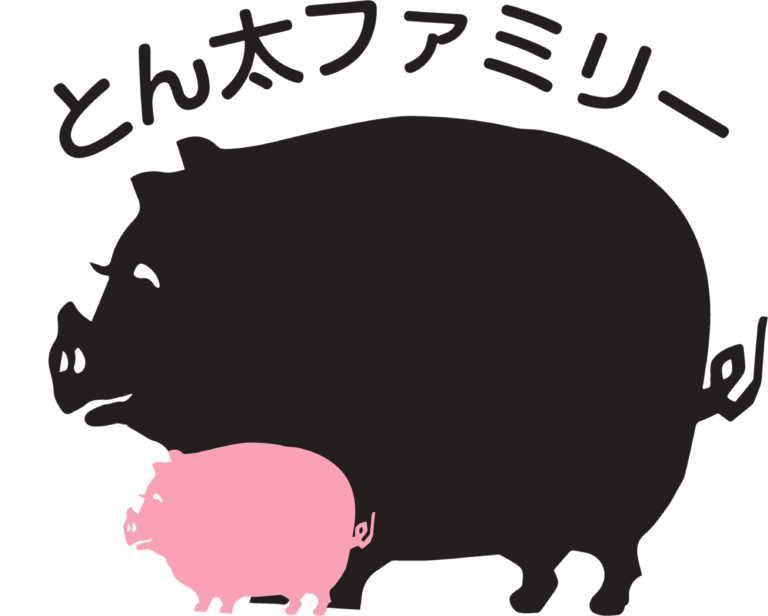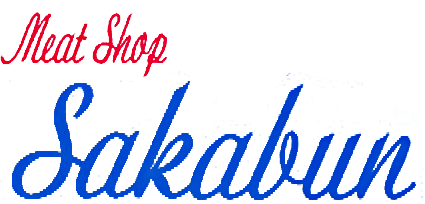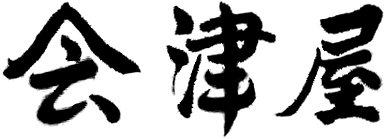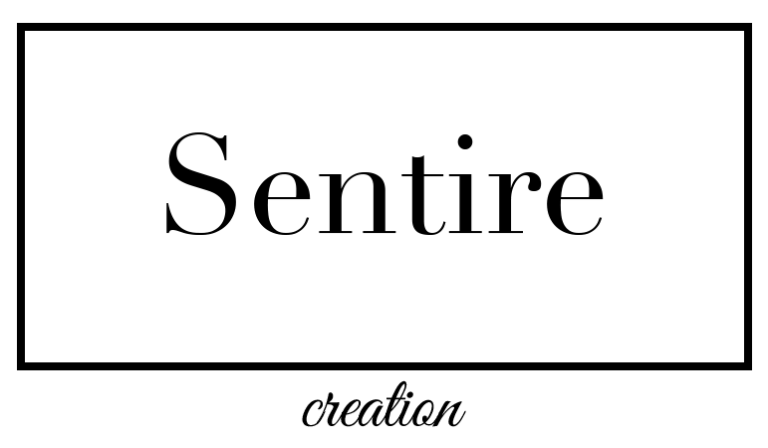日光産の杉材を中心とした各種木材の製材・販売を行っているのが、栃木県日光市に拠点を置く昭和2年創業の会社、株式会社ヤギサワ(以下、ヤギサワ)。
現在は3代目社長の八木澤 統隆(ともたか)さんが代表を務め、木材の製材・販売に加えて、不燃材をはじめとする特殊木材の開発・製造も行っています。
また国際的な森林認証制度に基づき、適切に管理された森林で生産された木材であることを示す認証材にも着目し、SDGs(主に目標15「陸の豊かさも守ろう」)への貢献など、視野の広い取り組みも進められています。
今回はそんなヤギサワの八木澤社長へのインタビューを通じて、次の切り口を中心にお話を伺いました。
|
製材所の業務内容
-ヤギサワの主要事業である、製材について教えてください。
自分たちを含め、多くの方にとって製材ってあまり馴染みがないように感じています。
八木澤社長:
基本的な仕事内容は、仕入れた丸太を挽いて(角・板材などに加工すること)、それを販売するのがメインです。
建材・エクステリア材として、昔から大工さんにも売ってますし、業販と小売の両方に対応する形で販売してます。
そうですね。今でこそあまり馴染みがないと思うんですが、昔は製材って身近にあったんですよね。

-確かに、昔の家を思い浮かべると、あらゆる箇所が木のイメージです。
むしろ今のように鉄とかコンクリートは、ほとんど使われていないのかもしれないですよね。
八木澤社長:
そうなんです。
そういう意味で言うと、木を加工して使う、製材っていうのは身近にあったんですよね。
元々、うちの会社はおじいちゃんが大工から始めて、製材に移って行ったんですけど、昔の家って木がたくさん使われているじゃないですか。
それで山からたくさんの木が降りてくるのを見てて、それで製材を始めたみたいなんです。

-特に昔は生活になくてはならないものですもんね。
八木澤社長:
そうですね。
なので会社の場所は、昔と少しだけ変わってますけど、昔からこの日光地域の木を製材していて。
-地域の人々の生活に根付いた事業というか。
八木澤社長:
そうですね。栃木県の主に日光地域の木を使ってて、それで経営理念も作ったんですけど。
「森林資源を活用する木材生産を通して、地域資源と社会を繋ぐ架け橋となり、資源、空間、環境に寄与することで、人が働く価値を創造する」っていうね。
長いんですけど、要するに「山にある素材を社会で使えるようにするには、うちの会社がないとできないことだよ。」っていうことを言いたいんですよね。
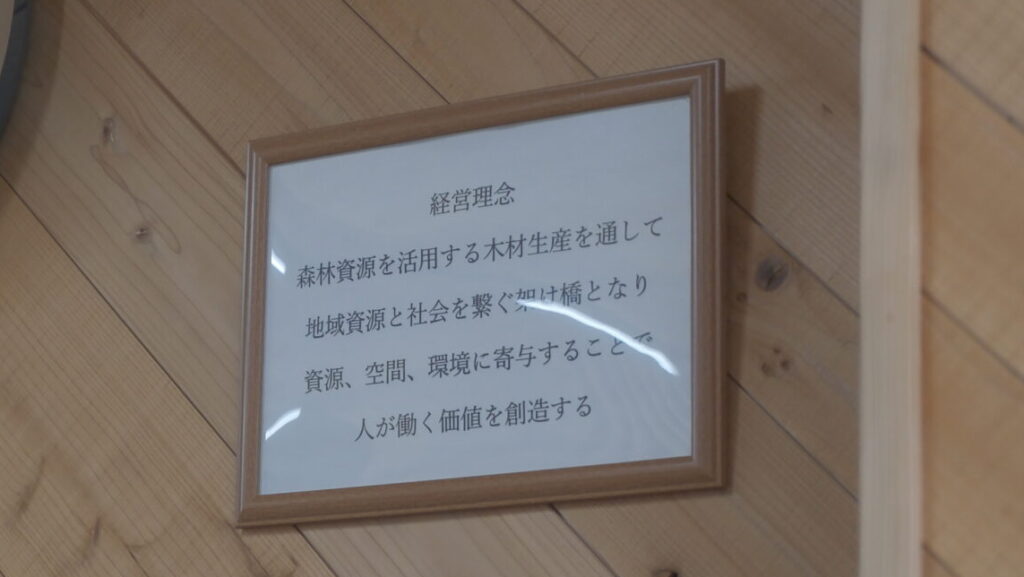
-椅子もテーブルも身の回りには木が使われているもの、たくさんありますよね。
そう聞くと製材が前より身近に感じられるようになってきました。
木材に変わる素材の登場について
-最近、樹脂のような木材に変わる素材を使って、3Dプリンターで建物を作るという流れが出てきてます。
木材とイコールではないと思うのですが、こうした流れに対して、どのようにお考えですか?
八木澤社長:
そうですね。まず木材の需要って世界的にあって、それでいうと木材は国際商品なんですよね。
うちではまだトライアルでなんですけど、県の事業とか、輸出で台湾とかに持ってったりもしてて。
日本からアメリカに輸出とかしてる例もあったりとかして、丸太で輸出するところもあるんですよ。
九州の方では、結構、中国に丸太で輸出しちゃうんですけど。

-価値を高めないで、素材のまま製材せずに、売ってしまっているというか。
八木澤社長:
そうそう。
それだと国内生産を伸ばせないし、価値を高めないで売っちゃうのは、もったいないことで。
-その点、日本の家電や車って海外で評価されていると思うんですけど、木材も評価されるものなんですか?
八木澤社長:
評価というか、少し別の視点になってしまうんですけど、そもそも日本には資源が豊富にあるんですよね。
しかも持続可能な。
日本ほど人工植林している、その素材(木材)を抱えてる国って、世界的にもあまりないんですよね。
ヨーロッパの方はフィンランドとかスウェーデンとか、他にはカナダとかアメリカの木材も結構、天然林なんです。
なので資源の確保が結構、難しくなってくる可能性があって、それからSDGsとかもあるじゃないですか。
-SDGs的な持続可能性のような点で言うと、木材は木材なので、樹脂とか3Dプリンターとはまた違うものなのかもしれないですね。

日本では、そこまで木材が大切だって思われてないかもしれないけど、海外では資源として大切にされてるんです。
でも日本はやっぱ豊かすぎるのかもしれないですよね。
資源に恵まれすぎて、資源の大切さを理解しきれてないというか。
どうしても、そういう部分もあると思うんですよね。
-正直、資源が豊かという認識があまりなかったです。
でも人口植林のお話を伺ってから、木材のことを考えると世界的にも恵まれている方なのかもしれないですね。
SDGsや持続可能に着目したきっかけ
-先ほどのお話で、SDGsや持続可能というキーワードが出てきましたが、そういったことに目を向けるきっかけとなった出来事などありますか?
八木澤社長:
木材のサスティナブルツアーと称して、10何年か前にオーストリアに行ったんですけど、それが影響してるかな。
オーストリアでは地域へ熱供給するために、ウッドチップのボイラーを住宅に張り巡らせていて。
(※ヤギサワの事務所でも、ウッドチップを燃やした熱エネルギーを暖房に活用されています。)
さらにいうと、その暖房の熱を料金として取っててね。
そういう地域熱供給の仕組みがあったんですけど、それを見ててかな。

-日本ではあまりイメージできないですけど、世界ではそういう持続的な熱供給の仕組みが確立されつつあると。
八木澤社長:
そう、それでヤギサワ村(ヤギサワの木材を使用されている事務所近くのアパート)の時にやりたいなと思ってて。
そもそもヤギサワ村の設計も、そのヨーロッパツアーをアテンドしてくれた人が設計してくれたんですけど。
その時にやりたいって言ったら、ちょっとまだ早いんじゃないかみたいな話になって、やらなかったんですけど。
今思えば機械もね、まだ古かっただろうし。
でも今やってもいいかなと思うんですけどね。
-ヤギサワ村とても素敵だったので、以降のアパートなどで導入を期待したいです。
個人向けにも販売する理由
-木材の販売は法人向けが多いのかなと思っていたんですけど、個人にも販売する理由は何かありますか?
製材会社というと、法人にしか卸さないっていうとこも多いイメージでした。
八木澤社長:
昔から大工さんにも売ってますけど、個人であっても「木材欲しい!」っていう方にはやっぱ売りますよ。
業販の方からも問い合わせ来ますけど、設計からも問い合わせ来ますし、あとは工事業者とか。

-法人に注力してしまった方が、売り上げを伸ばしやすいというのが一般的な見方なのかと思うのですが。
八木澤社長:
それはそうですよね。
でもやっぱり「木が欲しい!」っていう、その想いには、業販も個人も関係なく、できるだけ応えてあげたいって想いますし。
-お電話対応1つとっても、個人の方が相手でもすごく丁寧な会社だという印象を受けました。
どうしても個人だと、売上にならないから相手にできないという業者さんもいるのかと思ってたのですが、それはヤギサワの素敵な在り方といいますか。
八木澤社長の思い描く社長像
-しばらく前から日本では後継者問題が深刻化していますが、製材業界ではどうでしょうか?
ヤギサワでは30代前後のスタッフさんが多い印象なのですが。
八木澤社長:
そうですね。
うちは比較的若いスタッフが多いですけど、周りでは跡継ぎがいるのは、やっぱり多くはないかもしれないですね。
自分も37かな、その時に交代したんですけど、自分から交代しない?って言って相談をしたんですけど、日本の社長の年齢も平均年齢も60歳くらいでしたっけ。
社長の椅子に座っていたいってのはあると思うんですけど、自分の場合は会長でもいいんじゃない?って声かけて。
正直、何が正解かわからないですけど、成功したら社長じゃなくて、早く社長交代して主権を握るっていうのもね。
日本だと成功した人が社長みたいな感覚もあるかもしれないんですけど、自分的には1番色々なものにチャレンジして、回していくのが社長の姿だと思うんですよね。

-すごく響きました、今の言葉。
それで言うと、自分もあれやれこれやれって、スタッフに言って色々失敗してと言うのもやはりありまして…。
八木澤社長:
(笑)
いや、もう本当に今こうやってあるけど、色々チャレンジもしたし、その分、失敗も。
でもそれで、これはダメなんだなって、やっぱり失敗しながらわかってくもんだし。

-ありがとうございます。
なんだかインタビューの最後にパワーいただいてしまいました。
八木澤社長:
(笑)
だから自分もこれから何やっていくのか?みたいな時に、木材を使って家電メーカーになってもいいんじゃないか?とか。
今はLEDだから熱があんまりないじゃないですか。
そういうの使ってなんか照明とか作ってもいいかな?なんていうのも本当に考えたりとかして。
-家電と製材、一見すると全然違うものかもしれないですけど、それが色々なものにチャレンジしていく。
社長の姿ということですよね。

八木澤社長:
そうだね。
あと社長交代のことで言うと、元気なうちに交代してわからないことがあれば、聞けばいいだけで。
最初から完璧な社長をできるわけじゃないんで、交代だけとりあえずして。
それで伴走期間もあるっていうのも、やっぱいいなと思ったしね。
-早ければ伴奏しやすいということですよね。
社長の引き継ぎを考える方に参考になったのではないかと思います。
それでは一旦こちらでインタビュー、終えさせていただこう思います。
本日はありがとうございました。

以下の関連記事では、ヤギサワの工場見学の様子を中心にご紹介しています。こちらも併せてぜひご覧ください!
関連記事